書籍情報
今回は、理学療法マネジメントシリーズの「足部・足関節理学療法マネジメント」について紹介していきます。
この書籍は、臨床経験が浅く、足関節の疾患に悩んでいる現状に対して羅針盤となる一冊です。
足関節の疾患を担当したけどまず何をしたらいいの?足関節疾患に必要な評価ってなんだっけ?と迷える人を導きます。
本書は、基本的な機能解剖学とバイオメカニクス→病期別のポイント→機能障害→ケーススタディという流れで丁寧に説明しています。
基本的な機能解剖学とバイオメカニクスでは、臨床に特化して関節形状と運動軸の話から入り、多くの図や表でバイオメカニクスの内容を記載しています。
引用している文献数も多く、平均して30〜40。多くて100近く引用しているもの部分もありました。
主に機能障害に関して重点を置いていて、各機能障害に対する基本知識、評価、運動連鎖による影響、アプローチが手順だって記載されています。
- 整形分野で勤務してまもないセラピスト
- 足関節の疾患を担当したセラピスト
- これから足関節疾患で学会に症例発表や文献を書きたいセラピスト
その中でも、特に参考となる知識3つを紹介していきたいと思います。
距骨下関節アライメントの評価 ”Leg-heel aligment”
Leg-heel aligmentとは、荷重位および非荷重位において下腿長軸と踵骨長軸が前額面上でなす角と定義されています。
健常者を対象とした報告では、非荷重位では軽度内返し(1〜8°)、荷重位では軽度外返し(3〜7°)が平均とされています。
臨床では、主に荷重時の過度な内返しや荷重時の過度な外返しの有無を確認するが、踵骨二等分線の計測誤差は6°程度生じるとも報告されており、計測時には注意が必要です。
アキレス腱付近の脂肪組織 ”Kager’s fat pad”
Kager’s fat padは、アキレス腱と長母趾屈筋腱と踵骨に挟まれた三角形の空間に存在する脂肪組織です。
この脂肪組織は
①アキレス腱関連領域
②長母趾屈筋関連領域
③踵骨滑液包ウェッジ
に分けられます。
それぞれの領域に役割があり、足関節底背屈時のアキレス腱の滑走性やenthesis organ(腱付着部構造の破綻を防ぐためにその周囲に存在する組織、滑液包、滑膜性脂肪組織、線維性軟骨組織、骨組織などの複合的な器官)の圧迫力の軽減に関与してます。
荷重位での足関節背屈ROMと足関節捻挫の発生リスクについて
踵を浮かせずに最大背屈し膝が壁に接する肢位において、足趾先端から壁までの距離、もしくは下腿前傾角度を計測する。
その下腿前傾角が34°の場合、平均角度である45°に比べ、足関節捻挫の発生リスクが約5倍高くなります。
一方で、下腿前傾角が49.5°より大きい場合も足関節内返し捻挫の再発リスクが1.12倍高くなるとされており、背屈可動性の制限だけでなく過可動性にも注意が必要です。
さいごに
今回は「足部・足関節理学療法マネジメント」について紹介してきました。この書籍は臨床をもっと豊かにすることができ、評価から治療の流れや解釈をどのようにすればいいか導いてくれる本です。
足部は複雑でわからない、まず何を意識して取り組むのだろうと悩んでいる方は多いと思います。
ここでは、そんな悩みに対してこんな感じだよとよくある疾患を引用しながら、足関節に強い先生達が、考え、工夫し、より臨床を意識できる形で完成させたものです。
そんな偉人達の力を借りつつ、今立ち向かってる患者さん、これから出会うであろう患者さんを助けていきましょう。
このように「知ってる」と「知らない」で助けられる患者さんの数が変わります。
目の前の人を救うきっかけとして、この記事が参考になれば幸いです。

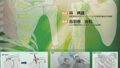

コメント